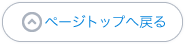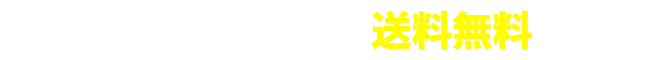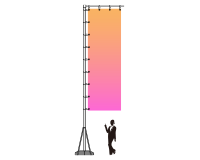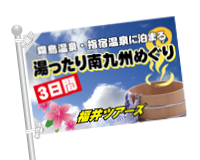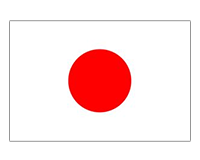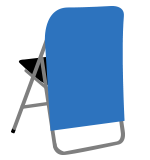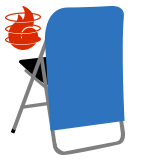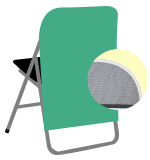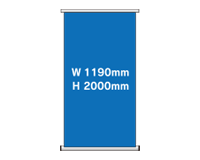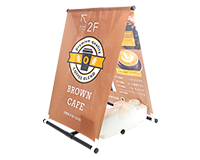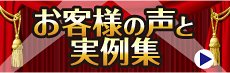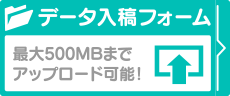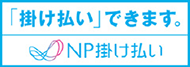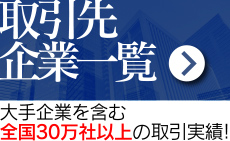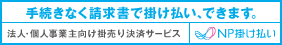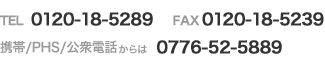のぼり屋さんドットコムTOP > のぼりのノウハウ > 展示ブース作成のコツを解説!作成時の注意点も紹介
展示ブース作成のコツを解説!作成時の注意点も紹介
更新日:2024年8月 9日 15:10
展示ブース作成のコツを解説!作成時の注意点も紹介

展示会に出展する際は、来場者を引き付ける展示ブースの作成が重要です。しかしどのような工夫をしたら良いのか、悩んでしまう方もいるでしょう。そこで本記事では、展示ブースを作成する際のコツと注意点を解説します。
展示ブース作成のコツ
展示ブースを作成しても、来場する人がいなければ意味がありません。自社の製品やサービスを宣伝する展示ブースを作成するには、以下に挙げるコツを意識してみましょう。
展示の目的を明確にする

展示ブースを作成するには、まず展示の目的を明確にすることが重要です。もし目的が不明瞭なままで展示ブースだけ作成を進めてしまうと、何を展示して誰をターゲットにするかが曖昧になってしまい、展示ブースの効果が十分得られない可能性があります。
自社の製品やサービスの認知度アップや見込み顧客の獲得など、あらかじめ目的をはっきりと決めてから、展示ブースを作成しましょう。
商材の性質に応じてブースの型を決める

展示ブースは以下の4種類の型に分けられ、商材の性質によって適した型が異なります。展示の目的を決めておけば、ブースの型を決めやすくなるでしょう。
- 製品展示型:自社製品を展示するタイプのブースです。展示した製品を実際に見てもらえるので、特徴などを理解してもらいやすくなります。展示すると店舗のような見た目になり、展示の方法によって得られる効果が左右されます。
- 製品体験型:製品を直接体験できるブースです。体験スペースを用意する必要があるため、広いスペースを準備する必要がありますが、実際に体験しなければ分からない特徴やサービス内容の理解促進が期待できます。より理解を深めてもらうため、上記の製品展示型と組み合わせる方法もあります。
- セミナー型:出展中に定期的にセミナーを開催する、無形商材向けの展示ブースです。多くの来場者を集めるために、広いスペースが求められます。セミナーの内容の良し悪しが効果を左右するので、展示ブースとしては難易度が上がる型です。
- 商談特化型:商談を進めることを目的としたブースです。すでに認知度が高い製品やサービスに使用されることが多く、複数の商談を行うために、顧客と座ってじっくり話せる商談スペースを十分確保する必要があります。
魅力が一目で伝わる装飾を考える
できるだけ多くの人に展示ブースで足を止めてもらうには、ブースの装飾を良く考える必要があります。展示会でとにかく目立つ装飾をすればいいのではないか、と思われがちですが、ただ派手に目立つだけでは何をアピールしているのか理解しにくく、足を止めてもらう要素とはなりません。
一目で何があるのか、どのような魅力がある製品やサービスを提供しているのかをわかりやすく、ポスターやパネルなどで目を引くのが、効果的な展示ブース作りのポイントです。
入りやすさを演出する
多くの人に足を止めてブースを見てもらうには、入りやすさも重要なポイントです。端から見て活気がないブースやスタッフが待ち構えているブース、閉鎖的なブースは入りにくさを感じるでしょう。
入りやすさを演出するには、自由にブースを見られるように開放的な導線を作る、一目で内容がわかりやすいようにパネルやポスターなどを設置する、スタッフが動的待機をして圧迫感を減らすなどの工夫が必要です。
展示品の数を絞る
製品を展示するブースでは、あまりたくさんの製品を並べてしまうと何を見ればいいのか迷ってしまい、来場者が疲れてしまいます。また展示品が多すぎると、何をアピールしたいのかが分かりにくくなってしまいます。
分かりやすい展示にするには、展示品の数を絞り込みましょう。展示品が少ないほど製品一つひとつに注目度が集まり、来場者の印象に残りやすくなります。複数の製品を展示したい場合はシンプルに、メインとサブの製品を設定しておくのもポイントです。
五感を刺激する空間にする
ただ展示をするだけではなく、五感を刺激する空間づくりが、来場者を集めるコツです。映像や音楽を取り入れたり、印象的な装飾を施したりするなどすると、来場者の五感を刺激し、印象に残るブースになります。
第一印象は来場者がブースに入るかどうかも左右するポイントなので、印象的な空間を作ることも、展示ブースを作成する際のコツです。
展示ブース作成時の注意点
来場者にとってわかりにくい展示や入りにくいブースは、成果を上げにくくなってしまいます。以下でご紹介する注意点を参考に、展示ブース作りを行ってみましょう。
社名だけを押し出さない
社名だけを前面に押し出すことは、まず避けたいポイントです。来場する側で考えると、知らない社名だけが目に付くブースには入ろうという気にはならないでしょう。
社名だけが押し出されていると、肝心の製品やサービスを知ってもらう機会が減りかねません。社名よりも、製品やサービスを押し出せるブース作りをしましょう。
装飾だけでなくスタッフの配置も考える
前述の通り、スタッフがブース内で待ち構えているブースは入りにくいものです。そこで、スタッフが作業などをしながら来場者へ声掛けなどをする動的待機に切り替えると同時に、効率的にブース運営を進められる配置も考慮します。
接客やプレゼン、契約などそれぞれの業務でスタッフの役割分担を行って人員配置を行うと、効率的なブース運営ができるでしょう。
まとめ

展示ブースはただ目立つだけでは来場者を集めることは難しく、興味を持ってもらえる機会も得られないため、人を集められるデザインや空間作りが重要です。今回解説
した展示ブース作りのコツや注意点を押さえて、魅力的で効果的な展示ブースを作ってみましょう。
記事一覧

- 生徒募集のぼりは効果ある?成功ポイントを解説

- スグ使える!夏ののぼり旗アイデア&売上アップ術

- のぼり旗 デザインのコツ|春の販促で映える作り方

- すぐ破れる・倒れるを解決!のぼり旗の「風対策」と長持ちさせる補強テクニック

- 冬こそ「のぼり旗」が効果的!寒い季節に人を呼ぶデザインと設置の鉄則

- 不動産ののぼり旗の種類は?効果的なデザインのポイントも解説!

- のぼり旗を自作する方法とは?作る際のポイントも紹介

- 視認性の高い色の組み合わせとは?のぼり旗を目立たせる方法を紹介
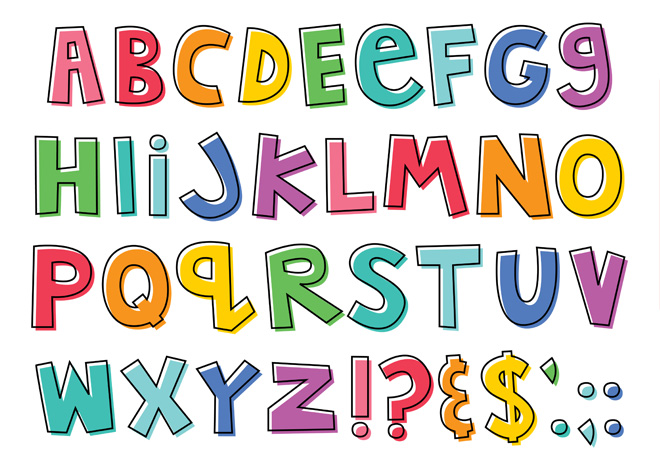
- のぼり旗の見やすいフォントはどのようなもの?フォント選びのポイントを紹介

- 文字を目立たせるテクニックは何がある?【集客に効果的!】
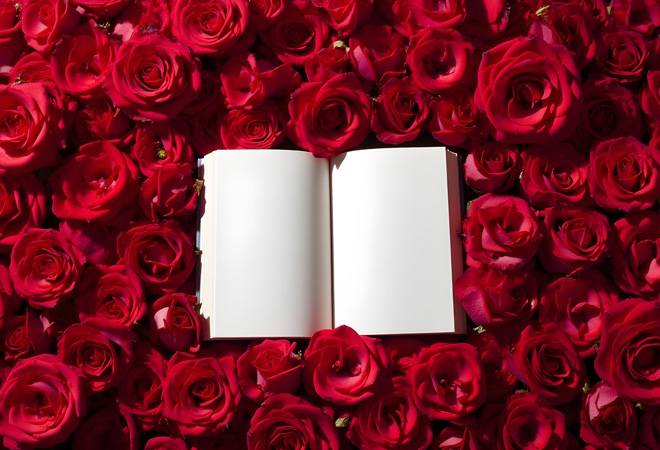
- 有名なキャッチコピーを参考にメッセージの伝え方を紹介!
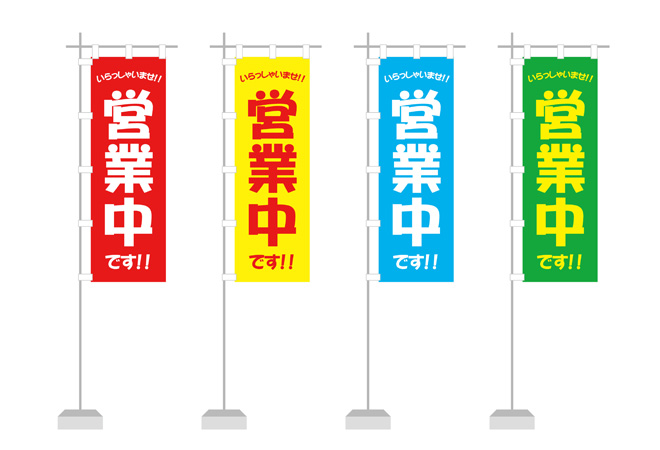
- 目立つ色や配色はどう選ぶ?色の例を解説

- ひもがほどけない結び方は?具体的な結び方を解説

- のぼり旗を初節句に飾ろう!種類や選び方を解説

- のぼり旗の設置はどう行う?組み立て方法や設置のコツを解説

- インクジェット印刷とは?仕組みやメリット・デメリットを解説

- のぼりの耐久性はどのくらい?長持ちさせるコツや適切な交換タイミングを解説

- のぼり旗で集客を増やすには?製作のポイントを解説

- かっこいいのぼり旗をデザインするには?製作のポイントを解説

- のぼり旗を防炎加工する方法は?防炎加工をするべき理由や保管時の注意点も解説